特許コラム
2010年10月19日 火曜日
「おせっかい教育論」
「おせっかい教育論」(鷲田清一、内田樹、釈徹宗、平松邦夫著 140B)を読みました。
この本を読んで思ったのは、
「こういう本が売れればいいのにな」
ということでした。
この本を出版している140Bは、今、ホームページ(http://www.140b.jp/index.php)のトップを見ると、
「オモロいか、オモロくないか、それが最重要課題です」
とあるわけです。
本当にそうですよ。どんなことでも、「オモロい」かどうかは重要だと思います。少なくとも本を作る人とか、自分の考えを人に伝えたい、と思っている人にとって、いかに人を引き付けて「面白がらせるか」ということは重要なことでしょう。
それは小説等の「面白いかどうかが重要」と誰もが思っている本に限らず、硬派な内容のものであっても、「人に伝える」のであれば、「オモロい」かどうかはすべて、といってもいいような気がします。
しかし、現実には、そうはいかないです。わざと「面白くない」ようにすることで、高尚に見せているものは多いですし、「面白いものは下賤」という考えもあるように思います。伝えようとしている内容によっては、「面白くできない」というものも世の中に多数あるので、「面白くないものは値打ちがない」とは言えないのですが。
でも、「面白くないものが面白いものより偉い」というわけでは絶対にないでしょう。同じ内容なら面白いに越したことはないはずです。
そういうなかで、「教育論」という本質的にお堅いものについて「オモロい」ものを提供することは本当に難しいことだと思います。
私はこの140Bという会社の出版物を他に読んだわけではないのですが、とりあえずこの本については、「お堅いこと」についての「面白い本」だと思います。そういう意味で、「オモロい」本を出すんだという意気込みは、「多くの人に読まれる」という形で成功して欲しいな、と感じます。
この本のもとになったのは、2009年10月1日に中央公会堂で行われた「ナカノシマ大学キックオフ記念セミナー」なのですが、私、このセミナーを受講していました。
このセミナー自体、非常に面白いものでした。まあ、面白いセミナーだったからこそ、本にしても面白いわけですが。
もう1年も前のことになるのですが、こうやって本を読んでいるとあの時の雰囲気やお話を聞いていたときの興奮のようなものが改めて蘇るような気がしました。「あーそうそう、そういえばそんな話が……」なんてことを思いながら読んでいました。
この本は主に「教育」ということについて書かれている本です。4名中3名は大学の先生ですから、「教育」については実際に現場で仕事をされている方です。そして、平松氏は大阪市長ですから、その仕事は教育と密接な関係があります。
私自身は教育にかかわる仕事をしているわけではありません。しかし、帯の内田樹氏の
「・・・(前略)自己利益を達成するために人は教育を受けるのだという思想が広まってしまった。それが教育崩壊の根本にあるのだと思います」
という言葉は考えさせられるものがありました(その詳細は是非、本書を読んでご確認下さい)。
結局、教育について考えるということは社会を考えるということだし、社会を考える上で教育は重要な手掛かりになるように思います。
知財についても、
「特許事務所の経営は、「金儲け」という自己利益の達成を最終的な目的にすることが正しい」
という前提が存在することに、この本を通じて気付かされます。
しかし、それについて「本当にそんな考えでいいのか」とずっと思っていた私にとって、「共同体の維持」に基づいて教育を論じるという本書の考え方はとても新鮮でしたし、自分の仕事への考え方につながることであったように思います。
このことは、単に教育にとどまらず、世の中の色々な職場で働く人が考えるべきことなのではないか、とも思いました。
「自己利益の達成」よりも「オモロい」かどうかを重視して仕事をしよう、ということは私もずっと考えていました。
現実には、それは簡単なことでないです。でも、そういう理念をなくしては、仕事がつまらなくなるだけなので、理想論と言われようとも、この気持ちを残していたいなと思います。
投稿者 八木国際特許事務所

![[JR新大阪駅 徒歩8分][御堂筋線西中島南方駅 徒歩10分][ホームページを見たとお伝えください]06-6484-6097 [受付時間]月曜~金曜 9:00~17:00 [定休日]土曜・日曜・祝日](http://www.yagi-tokkyo.com/images_mt/tel_number.png)

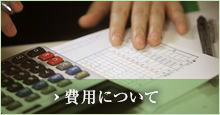


![[ホームページを見たとお伝えください]06-6307-2278](/images_mt/side_tel.png)
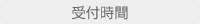




![[ホームページを見たとお伝えください]06-6484-6097](/images_mt/footer_tel.jpg)
![[受付時間]月曜~金曜 9:00~17:00 [定休日]土曜・日曜・祝日](/images_mt/footer_time.png)